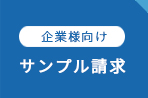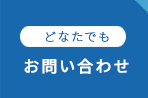海外向け商品販売基本規約
海外向け商品販売基本規約
発注者(以下「甲」という。)は、株式会社クリスタルプロセス(以下「乙」という。)の販売する商品(以下「本商品」という)の購入にあたり、海外向け商品販売基本規約(以下「本規約」という。)に定める以下の各条項を承諾した上で取引を申し込むものとする。
取引基本契約及び取引の内容
第1条甲は、乙に対し、本規約に定める条件のもとに、本商品の購入を行うものとし、本規約を内容とする契約を取引基本契約(以下「本契約」という。)とする。
2 本商品は、日本における必要な仕様・規格等に基づいて製造されたものである。一部の本商品は、甲が指定する仕様・企画等に基づいて乙で製造され、甲が指定する商標、商号、その他の表示(以下「本標章」という。)を付して乙から甲に供給されるものとする。
3 甲が乙に提供した仕様書通りに乙が本商品を製造したことにより、甲あるいは甲の顧客に生じた損害は、甲の負担とし、乙は一切の責任を負わないものとする。甲の乙に対する注文又は指図通りに乙が本商品を製造した場合も前段同様とする。
個別契約
第2条本商品の数量、単価、引渡期日、引渡場所、引渡方法、引渡費用(関税等取扱含む)、インコタームズ等は、取引の都度、甲乙協議のうえ、個別契約で定めるものとする。
2 個別契約は、甲が乙に対しメール等で購入希望内容を送付し、乙が甲に対して前項の事項等を記載したINVOICE(請求書)を送付の後、甲が承諾し合意した方法で代金を支払った場合に成立するものとする。
引渡
第3条乙は、本商品を、個別契約において指定された引渡期日までに、指定された引渡場所で甲に引き渡す。
2 乙は、本商品を個別契約において指定された引渡期日までに引き渡すことができないおそれが生じた場合には、甲に対し、直ちにその旨を通知し、甲乙は対応について協議するものとする。
検査
第4条甲は、個別契約に適合しないこと(数量過不足を含む)(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、本商品引渡後1週間以内に理由を記載した書面(メールを含む)をもって乙に通知をしなければならない。
2 前項の通知がなされないまま前項の期間が経過したときは、個別契約は契約不適合なく履行されたものとみなす。
3 乙は、第1項に定める契約不適合の通知を受け取り、乙がその事実を確認した場合には、代品または不足分の引渡しを行うものとする。
所有権の移転
第5条本商品の所有権は、甲による本商品の代金支払後、甲が本商品の引渡しを受けた時点で乙から甲に移転する。
危険負担
第6条本商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除いて乙が負担し、本商品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除いて甲が負担する。
代金の支払
第7条甲は、本商品の代金を全額前払いするものとし、乙の指定する支払期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。ただし、個別契約においてこれと異なる代金支払方法を定めた場合はその方法による。
契約不適合責任
第8条乙から甲に対して本商品を引き渡した後6ヵ月以内に、甲が本商品について直ちに発見することができない契約不適合を発見した場合、甲が乙に対して直ちにその旨を通知し、乙において本商品の契約不適合を確認した場合、乙は代品の引渡しを行うものとする。ただし、乙は当該発注金額を支払うことによって、この責任を免れることができるものとする。
製造物責任
第9条本契約に基づき乙が甲に引き渡した本商品が、第三者の身体および財産に損害を及ぼすことが予想される場合、乙は直ちに甲に連絡し、甲と協議して処理解決する。
2 乙は、本商品の欠陥(通常有すべき安全性を欠いていること)に起因して、第三者の生命、身体または財産に損害を生じた場合、当該損害を賠償するものとする。なお、乙は、賠償すべき損害の範囲および賠償額について、甲に協議を申し入れることができるものとし、甲は、誠意をもってこれに対応するものとする。
3 次の各号の一に該当する場合は、乙は、甲及び第三者に対して前項の責任を負わないものとする。
ア 乙が本商品を甲に引き渡した時点の科学技術水準では、本商品の欠陥を認識することができなかった場合
イ 本商品の欠陥が、本仕様その他本製品の製造に関する甲から乙に対する指示に従ったことに起因する場合
ウ 本商品の欠陥が公的機関の定めた基準に従って製造したことに起因する場合
エ 本商品の欠陥が、本商品の改変または乙の定める本商品の使用、保管、廃棄等に関する諸条件に違反したことに起因する場合
オ 本商品の欠陥が甲への引渡後に生じた場合
表明保証と必要な協力への同意
第10条甲は、本契約に基づく乙からの本商品購入について、当局手続きを含むすべての権限と能力を有することを保証する。
2 甲は、乙が取引銀行等から求められる情報提供について協力することに同意する。
3 甲は、乙が検査等に対応するために要請する協力について同意する。
秘密保持
第11条甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後であっても、本契約(個別契約を含む)及び本商品に関して知り得た一切の事項(技術上、営業上その他一切の情報であって、口頭、書面、電子的形態、図表、材料サンプルなど、いかなる形態であるかを問わない。)を厳密に秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならない。甲が公的機関の調査等のために開示をする際は、事前に書面(メールを含む)での乙の承諾を得るものとする。
2 甲及び乙は、前項の義務を自己の従業員にも遵守させるものとし、これらの者の義務違反は甲乙の義務違反とみなすこととする。
不可抗力免責
第12条天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本契約および個別契約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとする。ただし、金銭債務は除かれるものとする。
権利・義務の譲渡禁止
第13条甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、義務を第三者に引き受けさせることができない。
無断使用等の禁止
第14条甲は、本商品を販売するにあたり、甲の宣伝広告・ホームページ・販促物等において、乙の事前の承諾なく、①乙が製造する一切の商品に表示された製品の名称・キャッチコピー・商品ラベルのデザイン、及び、②乙の宣伝広告・ホームページ・販促物等の記載内容を使用してはならない。
2 甲は、本商品を販売するにあたり、乙の事前の承諾なく、乙が本商品について作成した表示及び説明内容を改変してはならない。
解除及び期限の利益喪失
第15条甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約の一つにでも違反したとき
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
(5) 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
(7) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 甲又は乙が前項各号のいずれかに該当した場合、当該当事者は当然に本契約及びその他相手方当事者との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当該当事者は相手方当事者に対して、その時点において当該当事者が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
損害賠償責任
第16条甲又は乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。
個別契約の効力
第17条個別契約の内容は、本規約に優先する。
規約の有効期限と乙による改変
第18条本規約の有効期限は特に設けない。
2 乙は、自社の判断と責任で本規約を改変できるものとし、常に最新のものを乙のHPに掲載して甲が確認できるようにする。
反社会的勢力の排除
第19条甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的支配を及ぼすと認められる関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行うことはできないものとする。
準拠法
第20条本契約および個別契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。
合意仲裁管轄
第21条本契約及び個別契約に関して争いが生じた場合、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁地は広島(日本)とする。
制定(最終変更)日 2025年4月1日